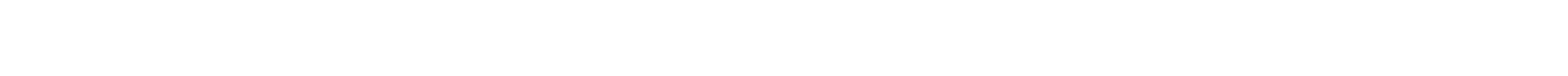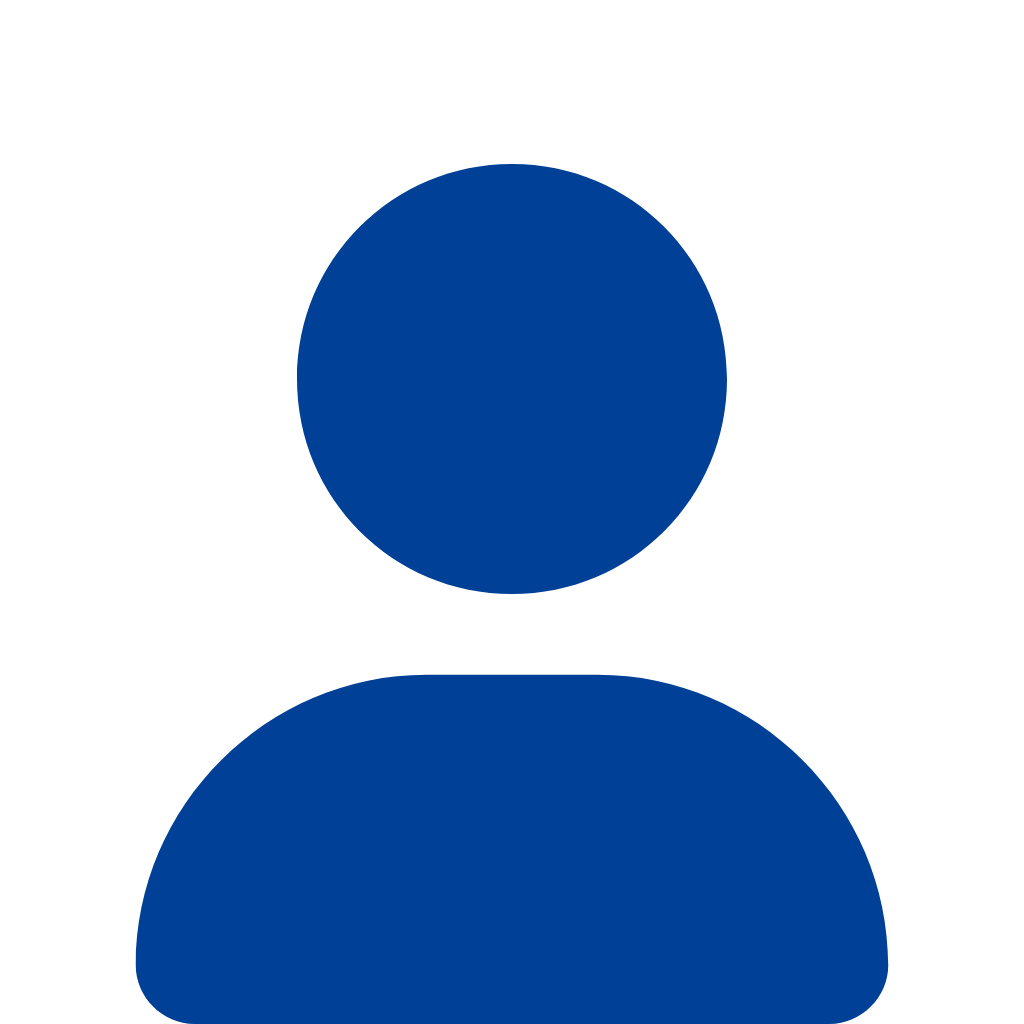プロダクトの仕様を検討する際、スムーズに決定が進まない(仕様がまとまらない)ことがあります。その要因として、部門間の立場の違いから考え方、視点の違い(意見の不一致)が挙げられます。しかし、「ユーザーにとって価値のあるプロダクトを提供する」という目指すところ、共通目標は同じであり、ベクトルは一致しています。にもかかわらず、意見の対立や意思決定の遅延が生じるのは、異なる視点を持つメンバー同士の考えをうまく調和させる仕組みが不足しているからではないでしょうか?
そこで、プロダクト思考とデザイン思考というアプローチを取り入れることで、仕様検討の円滑化に寄与できるのではないかと考えました。本記事では、それぞれの思考法の基本的な概念と違い、そしてバランスよく活用することで期待される効果について記載いたします。
プロダクト思考とは?
プロダクト思考とは、ビジネスの観点からプロダクトの成功を定義し、それを実現するために必要な要素を組み立てていくアプローチです。具体的には、以下のような視点を持ちます。
- ビジネス目標の達成: 収益性、成長戦略、市場競争力を考慮しながらプロダクトの方向性を決める。
- ユーザー課題の解決: ユーザーのニーズに基づき、最適な機能やサービスを設計する。
- 技術的な実現可能性: 開発リソースや技術的制約を考慮しながら、持続可能なプロダクトを設計する。
- データドリブンな意思決定: ユーザーの行動データを分析し、改善を繰り返しながらプロダクトを最適化する。
デザイン思考とは?
デザイン思考は、ユーザーの視点に立ち、課題の本質を理解し、創造的に解決策を導き出すアプローチです。以下のようなプロセスで進められます。
- 共感(Empathize): ユーザーの状況や課題を深く理解する。
- 問題定義(Define): 本質的な問題を明確にする。
- アイデア創出(Ideate): 多様な視点から解決策を発想する。
- プロトタイピング(Prototype): 具体的な形で試作し、アイデアを具現化する。
- テスト(Test): 実際のユーザーに試してもらい、フィードバックを得る。
デザイン思考は、ユーザーの行動や感情を理解し、仮説を立てながら試行錯誤することを重視します。そのため、ユーザーエクスペリエンスの向上に大きく貢献します。
プロダクト思考とデザイン思考の比較
| プロダクト思考 | デザイン思考 | |
| 目的 | プロダクトをビジネスとして成功させる | ユーザーの課題を解決し、満足度を高める |
| フォーカス | ユーザーに価値を提供できるか? | ユーザーが快適に使えるか? |
| 考える視点 | 市場・競争環境・技術の実現性・収益性 | ユーザーの体験・感情・使いやすさ |
| 判断基準 | データ、KPI、売上、成長率 | ユーザーの満足度、使いやすさ、直感的な操作性 |
| メリット | 開発の手戻りが減り、効率よく進められる | ユーザー満足度が上がり、問い合わせやクレームが減る |
どちらも重要な考え方ですが、一方だけに偏るとバランスを欠いてしまいます。例えば、プロダクト思考のみを重視すると、ビジネス面では優れた戦略が立てられるものの、ユーザー体験が軽視される可能性があります。一方で、デザイン思考のみを重視すると、優れたユーザー体験を提供できるものの、ビジネス的な持続可能性が損なわれるかもしれません。
両者をバランスよく取り入れることで期待できること
プロダクト思考とデザイン思考を組み合わせることで、以下のようなメリットが期待できます。
仕様決定の円滑化
ユーザー視点とビジネス視点の両方を取り入れることで、意見の対立を減らし、合意形成がしやすくなる。
より良いユーザー体験の実現
デザイン思考を活用してユーザーの本質的な課題を理解し、プロダクト思考でその解決策を持続可能な形に落とし込む。
市場競争力の強化
ユーザーにとって魅力的でありながら、ビジネスとしても成功するプロダクト(継続利用)を生み出すことができる。
チーム間の円滑な連携
営業、カスタマーサポート、開発チームが共通認識・課題(フレームワーク)を持つことで、より効率的な開発プロセスが実現できる。
まとめ
プロダクト開発において、ビジネスの成功を重視するプロダクト思考と、ユーザー視点を重視するデザイン思考は、それぞれ重要な役割を果たします。どちらかに偏るのではなく、両方をバランスよく取り入れながら開発を進めることで、仕様検討、意思決定が円滑になり、かつより価値のあるプロダクトを生み出すことができるのではないかと期待しています。
私たち開発チームは、これら考え方を試行錯誤しつつも前向きに実践し、より良いプロダクトを生み出していくことを目指していきます。